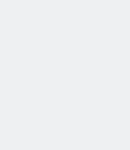月刊星ナビ 2020年6月号
あらすじ・内容
星空や宇宙、天体写真、望遠鏡に興味のある人のための月刊情報誌
3月に急増光し、大彗星になるのではと期待されていたアトラス彗星ですが、4月に入ると陰りが見え始め、ついには彗星核が分裂してしまいました。分裂はなぜ起こったのか? そして本当に大彗星の可能性はなくなったのか? 迷走を重ねた彗星の動向を解説します。
天文学の観測プロジェクトと聞くと大規模な装置を使うイメージがありますが、アマチュアでも揃えられる機材で、大口径望遠鏡に匹敵する成果を出した研究者がいます。太陽系外縁部にあるキロメートルサイズの小さな天体検出に成功したアイデアとは。
スコープテックから新発売となった片持ちフォーク式経緯台「ZERO」。口径8~10cmクラスの鏡筒を搭載し、高倍率の惑星観測でも実用になる架台を安価で実現しました。スルリと動いてピタリと止まる、剛性に優れたシステム経緯台のレポートです。
ステラショットで「都会の星雲・星団撮影」にチャレンジ。遠征するのはハードルが高いけれど、お家で撮れるなら気軽に始められます。空の明るい東京で、オリオン大星雲の撮影に挑戦しましょう。
6月10日は「時の記念日」。その誕生は、1920年に開催され、大成功を収めた「時」がテーマの展覧会までさかのぼります。今から100年前、東京が「響きの都」となったできごとを振り返りました。
ニュースやトピックでは以下の話題を取り上げています。
・「みおを、みおくろう!」水星探査機ベピコロンボ、地球スイングバイ
・「宇宙で働く」第3回 天文学者になろう
・日食カウントダウン 6月21日金環日食まであと1か月
・天文台マダムがVERAプロジェクトの危機を解説!
(C)AstroArts 2020
作品情報
シリーズ最新刊
実用 月刊星ナビ 2024年5月号
月刊「星ナビ」2024年5月号では、順調に明るくなっているポン・ブルックス彗星の見方、撮り方を特集しました。特別付録は「天体画像処理」の第5弾。人工天体の「狂」拡大や、陰陽師・安倍晴明、CP+2024といっためくるめくラインナップが満開です。
「1テーマ5分でわかる! 天体画像処理」も5回目。今回は「仕上げ編」の続きとして「詳細編集モード」の使いこなしに焦点をあてました。
夕方の西空で明るさを増しているポン・ブルックス彗星。太陽への最接近を前に、今夜から使える「見て、撮影する」ための実践的なテクニックを紹介しています。
宇宙ステーションを拡大してとらえる3名の愛好家が、それぞれの秘蔵ノウハウを伝授する「人工天体撮影虎の巻」シリーズ。2回目は「手動追尾と惑星面通過」をテーマにお届け。
大河ドラマ「光る君へ」で話題の陰陽師・安倍晴明。そもそも陰陽師とはどんな存在だったのか。天文や暦の観点からその存在に迫りました。当時の天文現象もステラナビゲータで再現。
2024年2月のリアル開催で、コロナ禍以前のにぎわいを取り戻したCP+をレポート。天体望遠鏡やカメラ周辺機器の最新ニュースをぎゅっと詰め込んでいます。
バーチャルサイエンスコミュニケータの北白川かかぽさんが、マインクラフトで遊べる月ワールド「ルナクラフト」を紹介します。2050年の月面を一緒に探検しましょう。
ニュースやトピックでは以下の話題を取り上げています。
・カイロスロケット 打ち上げ5秒で自律中断爆発
・連休中の注目天文現象 月と土星の接近、みずがめ座η流星群が極大、白昼の火星食
・天文台マダム、歌舞伎町のアカデミックな夜「学問バー」へ
・星の召すまま拡大版 超精密天文時計設計者のこだわり半生
「月刊星ナビ(星ナビ)」シリーズ作品一覧(全77冊)
835円〜1,500円(税込)
-
実用 月刊星ナビ 2020年8月号
木星と土星が相次いで見ごろとなっています。赤い大渦「大赤斑」や双眼鏡でも見える4大衛星で人気の木星。美しい環が魅力の土星。夜更けには、10月に地球に最接近する火星も昇ってきます。「夏の星空案内2020」で、惑星ざんまいの夏を過ごしましょう。
木星の写真を見ると、赤い目玉のような「大赤斑」が目につきます。色や大きさが絶えず変化してきた大赤斑の歴史や、惑星探査機による観測によって見えてきた深部構造、その誕生と終焉を考察し、初めて観測されてから350年以上にもなる不思議なスポットの謎に迫ります。
ディープな撮影派3名による、オーストラリアの南天星空旅行記第2弾では、旅の実際を座談会形式で紹介。海外遠征が可能になったら参考にしたいノウハウが満載です。
6月号の前編に続いて、「またたく宇宙をつかまえる」後編をお届け。感度や精度の向上で「動的な宇宙」を比較的安価な機材でとらえられるようになり、おもしろくなってきているアマチュア天文学の可能性を考えます。
星の和名をたずねて全国に足を運び、調査を続けてきた北尾浩一さん。集大成ともいえる『日本の星名事典』を出版後も、まだ知らぬ星の名を求め、各地を回っています。42年にも及ぶその旅路を辿りました。
ステラショットで「都会の星雲・星団撮影」にチャレンジする「ステラショットで撮らなきゃ損!」。連載3回目はいよいよ撮影スタートです。
ニュースやトピックでは以下の話題を取り上げています。
・6月21日 台湾で金環&日本全国で部分日食
・民間宇宙船「クルードラゴン」 アメリカが9年ぶりの有人飛行
・小惑星に姿を変えた神話の太陽ボーイズ
・小惑星パティエンティアによる恒星食
・宙ガチャでビクセンの大口径望遠鏡ゲットだぜ! -
実用 月刊星ナビ 2020年7月号
5月末時点で緊急事態宣言は解除されましたが、遠征や連れ立っての観望は難しい状況です。そこで、自宅や近所で星空を楽しむ「おうちで天文」の提案です。ベランダや庭、ご近所で夜空を見上げたり撮ったり、オンライン観望会に参加したりして、今を過ごしていきましょう。
6月21日夏至の日は、アフリカからインド、中国、台湾を通る金環日食です。そしてそれに伴う部分日食が、日本全国で見られます。全国各地での見え方や起こる時間、そして安全な観察方法とおすすめの撮影テクニックをご案内。
ディープな撮影派3名による、オーストラリアの南天星空旅行記。第1回は、3名それぞれの撮影戦略と準備、渡航用のパッキングノウハウを語ります。
ステラショットで「都会の星雲・星団撮影」にチャレンジする2回目。機材の組み立てから、難関のピント合わせに挑戦しました。
今年の6月10日は「時の記念日」が誕生してからちょうど100年です。「1秒」に注目しながら、「時」と天文学の100年の関係を紹介します。
90年の歴史をもつ京都大学花山天文台が、閉鎖の危機を乗り越えて存続されることになりました。多くのアマチュアを育てた聖地がめざす“夢”を描きます。
ニュースやトピックでは以下の話題を取り上げています。
・天文VTuber「宇宙物理たんbot」がクラウドファンディング開始
・小惑星パリスによる恒星食と6月の注目食現象
・新型コロナウイルスと天文普及 -
実用 月刊星ナビ 2020年6月号
3月に急増光し、大彗星になるのではと期待されていたアトラス彗星ですが、4月に入ると陰りが見え始め、ついには彗星核が分裂してしまいました。分裂はなぜ起こったのか? そして本当に大彗星の可能性はなくなったのか? 迷走を重ねた彗星の動向を解説します。
天文学の観測プロジェクトと聞くと大規模な装置を使うイメージがありますが、アマチュアでも揃えられる機材で、大口径望遠鏡に匹敵する成果を出した研究者がいます。太陽系外縁部にあるキロメートルサイズの小さな天体検出に成功したアイデアとは。
スコープテックから新発売となった片持ちフォーク式経緯台「ZERO」。口径8~10cmクラスの鏡筒を搭載し、高倍率の惑星観測でも実用になる架台を安価で実現しました。スルリと動いてピタリと止まる、剛性に優れたシステム経緯台のレポートです。
ステラショットで「都会の星雲・星団撮影」にチャレンジ。遠征するのはハードルが高いけれど、お家で撮れるなら気軽に始められます。空の明るい東京で、オリオン大星雲の撮影に挑戦しましょう。
6月10日は「時の記念日」。その誕生は、1920年に開催され、大成功を収めた「時」がテーマの展覧会までさかのぼります。今から100年前、東京が「響きの都」となったできごとを振り返りました。
ニュースやトピックでは以下の話題を取り上げています。
・「みおを、みおくろう!」水星探査機ベピコロンボ、地球スイングバイ
・「宇宙で働く」第3回 天文学者になろう
・日食カウントダウン 6月21日金環日食まであと1か月
・天文台マダムがVERAプロジェクトの危機を解説! -
実用 月刊星ナビ 2020年5月号
「バックラッシュが極めて少ない」「バランスウェイトなしの運用が可能」などのメリットで「波動歯車装置」を採用した赤道儀が注目されています。しくみから活用事例、各社の製品動向を網羅する大特集。望遠鏡架台の新しい技術潮流を追いかけました。
天体撮影ソフト「ステラショット」がこの春メジャーバージョンアップ。使いやすさをさらに追求し、星雲・星団撮影のすべてのステップにかかわる機能が大幅にブラッシュアップされました。新しいインターフェイス、別売オプションのGearBoxを使ったワイヤレス制御などを解説します。
昨年末にハワイで発見されたアトラス彗星(C/2019 Y4)が明るくなってきています。1844年に2等級になった彗星(C/1844 Y1)と同じ軌道を動いており、「大彗星の再来なるか」と期待されているアトラス彗星の予想光度はいかに? 4月から5月にかけて、夕方の空で観察してみましょう。
星図の中の生き物たちは制作者などによってさまざまな形で描かれています。その中の「かに座」を今回はクローズアップしました。果たしてかに座のモチーフとなるカニは存在するのでしょうか? 海洋生物学の視点から「かに座の蟹」の正体に迫ります。
2か月後に迫った6月21日の金環日食。アフリカからインド、中国を経て台湾へとユーラシア大陸を横断する金環食帯の中から、おすすめの観測地を案内。細い金環となる理由も併せて解説しています。
ニュースやトピックでは以下の話題を取り上げています。
・「誌上CP+」で新製品をバーチャルレポート
・鹿島 34m&11mパラボラアンテナが今年解体へ
・エーゲ海の風 輝けるハイスペック男神アポロン
・「宇宙で働く」第2回 プラネタリウム解説者 -
実用 月刊星ナビ 2020年4月号
春は銀河の観望・観測のチャンス。特集「ときめく銀河図鑑」では天文学の視点からさまざまな銀河を形と色で分類し、その進化を問い直します。「美しい」だけではない銀河の魅力にときめきましょう。
「宇宙・天文関係の仕事をしたい」と考えている人を応援する連載「宇宙で働く」がスタート。第1回は、宇宙開発の最前線で活躍する若手に「やりたい仕事の見つけ方」や「今の仕事をめざした理由」などリアルな経験を語ってもらいました。
6月21日の台湾金環日食。遠征におすすめなのが、金環食帯の中心線が通る南部の都市・嘉義です。夏至の日の正午に太陽が真上にやってくる「北回帰線」上に位置する都市でもある嘉義の見どころや、台湾の歴史を紹介します。
デジタルカメラや、赤道儀、オートガイダーを統合制御し、スマートな星雲・星団撮影を実現する「ステラショット」が「2」にパワーアップ。極限まで省力化、使いやすさを追求して、さらに洗練されたソフトになりました。
新発売となったオリンパスの「OM-D E-M1 MarkIII」に、星に特化したオートフォーカス機能「星空AF」が搭載されました。ボタンのひと押しで確実にピントを合わせてくれる、「星空撮影の革命」ともいえる機能を試します。
ニュースやトピックでは以下の話題を取り上げています。
・赤外線で見通す宇宙 TAO望遠鏡の2つの眼
・日本初の人工衛星「おおすみ」打ち上げから50年
・つくばエキスポセンター デジタルプラネ一新で広がる表現
・本年最高条件の恒星食 小惑星パリスが8等星を隠す
・4月初旬、プレアデス星団に金星がニアミス
付与コインの内訳
444コイン
-
会員ランク(今月ランクなし)
1%
-
初回50%コイン還元 会員登録から30日以内の初回購入に限り、合計金額(税抜)から50%コイン還元適用
複数商品の購入で付与コイン数に変動があります。
会員ランクの付与率は購入処理完了時の会員ランクに基づきます。
そのため、現在表示中の付与率から変わる場合があります。
【クーポンの利用について】
クーポン適用後の金額(税抜)に対し初回50%コイン還元分のコインが付与されます。
詳しくは決済ページにてご確認ください。