これを記念して、ここでしか読めないカルロ・ゼン先生の書き下ろしショートストーリーを公開中です!!
第二〇三航空魔導大隊を基幹となし、歴戦の戦闘機械と名高いサラマンダー戦闘団。
帝国軍が総力戦で摩耗してなお、その卓抜した戦力は些かの曇りもない。なればこそ、帝国軍の高級指揮官らは『頼りになる』戦力として彼らを見つつ……壊れることのない精鋭とみなしがちだ。
そんな彼らとても、実のところ人間の集団である。
撃たれれば怖いし、叩かれれば痛いし、つまるところ戦場の恐怖と対峙し続ける『ストレス』は深刻極まりない。
情動を制御する戦争屋として規律訓練は徹底されている。感情を制御し、最善を尽くして生き残る野戦軍人へと加工もされた。仕上げとして砲火の洗礼をも存分に潜り抜けている。
だからこそ、サラマンダー戦闘団の将兵は実戦経験というこの上ない教師の教育を通じ、いついかなる時であろうとも『平常な世界での人間性』を保つ大切さは嫌と言うほどに知悉していた。
戦争とは非日常の連続だ。そんな空間においてさえ、敢えて『日常』という要素を保つことは緊張に打ち勝ち正気を保つかけがえのない時間である。
引き締めるべきところではどこまでも厳格に。されども、緩める余地があれば緩々と。
食卓を穏やかに囲めるのであれば夕べには、いつだって酒が欠かせない。
アルコール、或いは人類最良の友。
航空魔導大隊を基幹とする観点から、煙草の類が将校の間ではあまり好まれないことも大きく、その反動からも酒精は戦闘団内では広く愛飲されていた。
特筆に値するのは、その潤沢さだろう。
サラマンダー戦闘団将校用の『酒精』は滅多に不足しない。極端な話、一番最後に払底するといってもいい。その晩に飲む酒の心配をするのは、戦闘団の残弾を心配した後で良いほどなのだ。
大勢がほどなくして自然と悟るのだが、戦闘団長付副官たるセレブリャコーフ中尉の辣腕が目立たない形で発揮されている部分でもある。ヴィーシャの愛称で呼ばれることの
ほんわか副官という印象とは裏腹に、彼女はちゃっかり調達してくる。
賭け事に強く、酒にも強く、そしてギンバイのプロ。
のほほんとした彼女の意外な一面である。
なればこそ、イルドア土産とてばっちり調達であった。中佐殿差し入れのワインを筆頭に、各種お土産物を調達した彼女の手腕は戦闘団で高く……極度に高く評価されている。
帝都へと帰還し、再出発までの束の間を過ごすひと時。
こんな時には、飲むしかない。久方ぶりの平穏ともなれば、誰だって大いにゆっくりと自由と日常を堪能するものだ。そして夕餉において、ワインと食事という最高の組み合わせだ。
切欠は、偶々だった。
愛飲家のセレブリャコーフ中尉が音頭を取れば、非番だった副長が気まぐれで合流。そこへ誘われたグランツ中尉も同席し、戦闘団用に割り当てられた士官食堂で存分に美味を堪能する。
勿論、封を開けられるのは帝国では稀有と化しつつある赤だ。
「ああ、この赤ワイン。ほんと、イルドア土産で頂いたやつは最高ですよね……」
グラスを傾け、微かにセレブリャコーフ中尉は笑う。貧相な帝国の食糧事情とても、イルドア旅行で買い込んだチーズとハムがあれば話は全く別だ。フルボディの濃厚な赤で、Kパンの苦みを押し流す力技が行使可能となる。
もちろん、濃厚なウェットタイプのチーズと塩気のある生ハムを齧れば……いっそKパンですら味のあるパンと強がることも可能だろう。
この点、ヴァイス少佐もまた己の好みを満喫して憚らない。
「自分にとっては、酒よりも肉だな。……特に、サラミは失って久しい。イルドアのことが好きになれそうだ」
もぐもぐと肉を食らい、ぐびぐびと酒を飲む。二兎を追う戦略ながらも、一石二鳥の戦果を挙げているグランツ中尉もまた素直に喜びを口に出す。
「イルドア好きという点では、自分もです。副長の仰るように、こうもお土産を頂くと」
「肉? 酒?」
「肉も、酒もだよ! みれば、わかるだろ、ヴィーシャ!」
ははは、なんて笑い声と共にセレブリャコーフ中尉は首を軽くかしげる。
「ほんと、イルドアってそつがないというか……こういうの、上手ですよねぇ……」
ぽつりとこぼれるのは、感嘆符。
少なくとも、イルドアの『外交手腕』というのをこの場においては認めるに誰もがやぶさかではない。
「……少佐殿の仰る通り! だって、このワインですもんね。こんなに良いワイン! このお土産、たまらないですよ」
「ヴィーシャの言葉ではないですが、外交術の神髄を見る思いです。こう厚遇されると、中々悪い気になれないというか。風見鶏野郎に、笑顔の一つも見せたくなります」
副官とグランツ中尉の言葉に対し、ヴァイス少佐は苦笑交じりに顎を掻く。
実際、同盟者としての義務を果たさざるイルドアに対し愉快ならざる感情を抱いてしまうのは事実だ。
なのに、食品とワインで懐柔されかけている。
サラマンダー戦闘団最大の弱点は、食事である。肉、ワイン、チーズに対しては白旗を上げるしかない。歴戦の航空魔導士官三名がこぞって同意する曇りなき真実である。
無論、単なる航空魔導部隊を懐柔したところで帝国の対イルドア観を激変させるには至らないのだろうが……塵も積もれば山となるものだ。
ヴァイス少佐にしても、こういう息抜きの酒をくれた相手を憎く思うのは難しい。
イルドアはうまいものだな、と苦笑すると同時にふと疑問を抱く。そういえばデグレチャフ中佐は、いったい、どこで『息抜き』をしているのだろうか、と。
何気ない疑問だったが、ヴァイス少佐はそれを口に出していた。
「セレブリャコーフ中尉、副官としての貴官に聞きたいのだが。中佐殿はストレス発散で飲まれないのか?」
「はい?」
「我々で独占するのも……ん? どうかしたか」
唖然とした表情のセレブリャコーフ中尉の顔に思わず言葉を飲み込み、ヴァイス少佐は己の言葉を再検討する。
酔っぱらっているとはいえ、別に我を失って失言するほどではないはずだ。第一、今の会話におかしなことなどあっただろうか。
彼には、分からなかった。
だからこそ、呆れたような声でグランツ中尉が横から口を挟む。「いや、少佐殿。それ、無理ですよ」
「なにが無理なんだ、グランツ中尉?」
疑問を返されたグランツ中尉は、顔面に張り付けていた精悍さを放り出して困惑と唖然の色を浮かべていた。
いっそ、ぽかんとした……と形容するべきかもしれない。
流石にというべきか、ヴァイス少佐は状況を読み取っていた。自己の発言が両中尉を呆然とさせている事実を速やかに認識。原因究明のため、一時的に黙考し始める。
問題を引き起こしたと思しき発言はたった一つ。飲酒癖を問うことだろうか。だが、なぜ、このような反応を招くかは謎だ。
「なんだ、両名揃ってその顔は。何か、自分が変なことを?」
ヴァイス少佐の疑念に対し、おずおずとながら反駁するような視線が二つ。理解に苦しむとばかりに眉を顰める副長に対し、セレブリャコーフ中尉は流石に口を開く。軽い苦笑すら顔面に張り付けつつ、彼女は副長の誤りを指摘する。
「その……よろしいでしょうか。中佐殿のご年齢で飲酒したら一発で違反ですよ。飛行停止処分になってしまいますし、何より体質的に飲めるんでしょうか?」
飲めるのでしょうか、という一言には横に座っている7グランツ中尉も強く頷く。
「ヴィーシャのいう通りです。我々は忘れがちというか、普段は意識することもありませんが、中佐殿は法律上ではお子様ですからね」
ぽん、と手を打ちヴァイス少佐は頭を振る。
「……そういえば、そうだったな」
どうしてか、彼は上官を『デグレチャフ中佐』という単語で理解し、その『実年齢』など東部の泥濘にまき散らして忘れ去っていた。
なるほど、と納得したところでヴァイス少佐は更なる疑問を口に出す。
「中尉、中佐殿がストレス発散をどうやられているかご存知か?」
さぁ、とヴィーシャは首をかしげていた。
上官が大不機嫌なのは傍目からも察しが付くが、さりとて爆発するでもなく、何かに当たり散らすでもなく、強いて言えば書類と新聞を親の仇のように睨みつけるぐらいか。
ストレス発散に何か……と考えたところで当たり障りのない答えしか出てこない。
「よくわかりません。たぶん、珈琲とチョコじゃないですか? ヴァイス少佐と同じで、甘党でいらっしゃいますし。まぁ、最近は険しい顔をなさることも多いようですが」
ガジガジと板チョコを齧っていたことは、流石に口外しかねた。それを別とすれば、しかし、セレブリャコーフという副官の眼から見てもターニャ・フォン・デグレチャフという中佐殿は全くどこで息抜きをしているのかも理解に苦しいほど職務熱心である。
「状況が状況だ。無理もない。……厳しいな。いや、暗い話になってしまったな。おや、グラスが空いたのが原因らしい」
「もう一献いかがですか?」
「やめておこう。たしなむの程度ならばさておき、飲み過ぎるとどうにも酒癖がな」
そのヴァイス少佐の自嘲じみた言葉に対し、グランツ中尉が深々と頷く。
「壊れますからね。酔いつぶれた少佐殿、重たいんですよ。いつも担いで帰る男衆の身にもなってください」
「だから、気を付けているのだろう? さて、自分はこの辺でお暇しよう。寝酒には良い量だったしな」
その言葉と共に、あっさりとヴァイス少佐は席を立つ。
元より軽い夕餉。食べ終えたらば、寝るのも悪くはないだろう。もっとも、酒が飲める人間にとってはまだボトルが残っているのでお開きには少しばかり勿体ない。
そういうわけで、会話をアテにヴィーシャとグランツの両中尉はゆっくりとグラスを空けていく。
「……しかし、最近はなぁ。確かに、きつい。酷使というか、使える人間はとことん迄扱き使われる毎日です。中佐殿も、あまり明言はされませんけどお疲れなんじゃないかなぁとは思いますね」
「ヴィーシャでも聞けないものか?」
私が? というようにポカンとするセレブリャコーフ中尉へグランツ中尉は疑問を投げかける。
「それこそ副官で、中佐殿とは長いだろう? 愚痴の一つも耳にしたかと」
「あの中佐殿ですよ?」
なにしろ、とセレブリャコーフ中尉は嘆いて見せる。
「ラインで私が初陣を迎えたころ、私は死にそうでした。その横で平然と野戦糧食に文句をつけていた方なんですからね、中佐殿は」
とても、聞けませんよと言うほかにない。
実際、神経というか感性が違うのだ。今でこそ、ヴィーシャ自身もベテランと呼ばれる部類ではある。けれど、新兵の時分、あれほど肝の据わったデグレチャフ少尉殿が上官だったのは良かったのか、悪かったのか。
間違っても、自分があの立場であればストレスで斃れていたと思う。シュワルコフ中尉はまだしも、やはり、デグレチャフという上官は理解が難しい。
「……ラインは酷かったもんなぁ。なのに、今では東部の泥濘から南方の砂漠に海に、次はまた西方航空戦だ」
グランツ中尉の珍しい弱音に、彼女もまた小さく頷く。
「ほんとに。とはいえ、……慣れるもの、か」
「全くだ」
まぁ、と両者して共に苦笑する。
『この緊張だけは、中々にきつい』と。

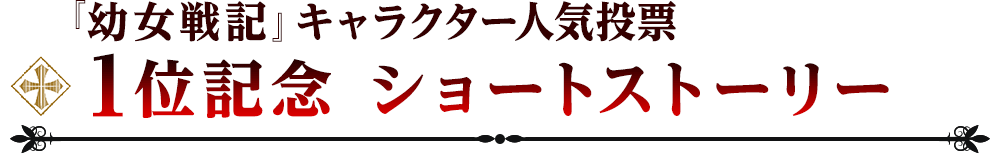



 トップページへ
トップページへ